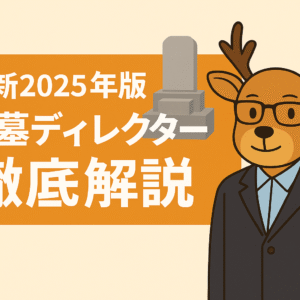終活カウンセラーとは?試験内容・取得のメリット・デメリットまで解説!
高齢化が加速する今、「終活」の重要性が高まり、終活カウンセラー資格への注目が急速に広がっています。しかし、終活は相続・お墓・葬儀・介護など領域が幅広く、何から準備すればいいかわからない…という方が多いのが現状です。
そこで本記事では、初めて終活を学ぶ方にもわかりやすく、終活カウンセラー資格の基本情報・取得方法・難易度・活かし方を徹底解説します。自分にとって必要な資格なのか、どのように仕事に活かせるのかが明確になります。
さらに、終活カウンセラーの年収目安や将来性、実務で役立つポイントも表と具体的なコメント付きで紹介するため、資格の全体像をしっかり理解できる内容になっています。ぜひ最後まで読み、あなたにとって最適な終活資格選びに役立ててください。
終活カウンセラーとは?
終活カウンセラーとは、相続・葬儀・お墓・介護・保険・生前整理など、人生の最終段階に関する悩みを総合的にサポートする“終活の専門アドバイザー”です。
終活は分野が広く、正しい情報を自分で集めるのは難しいため、多くの人が「何から始めればいいのかわからない」という不安を抱えています。
こうした課題を解決するために、終活カウンセラーは相談者の状況を丁寧にヒアリングし、必要な準備をわかりやすく整理します。
具体的には、
- 相続の基本的な流れの確認
- 葬儀やお墓の選び方
- 介護が必要になった場合の備え
- エンディングノートの書き方
- 適切な専門家(弁護士・税理士・葬祭業者など)への橋渡し
といった幅広い終活相談に対応します。
また近年は、親の介護や財産管理、葬儀の準備で悩む“子世代(40〜60代)”からの相談も増加しており、家族トラブルの防止や老後の安心づくりの観点から終活カウンセラーの需要はさらに高まっています。
終活カウンセラーは、専門知識だけでなく、相談者に寄り添うコミュニケーション力が重要なため、福祉・医療・介護・葬祭・保険などの仕事に携わる人はもちろん、家族の終活に備えたい一般の人にも役立つ資格として注目されています。
終活カウンセラーの資格区分は1級・2級があり、1級取得後に終活カウンセラー協会認定終活講師養成講座を受講し、試験に合格すると、終活カウンセラー協会認定講師として認定されます。
終活カウンセラーの試験概要
| 資格名 | 終活カウンセラー |
| 主催団体 | 終活カウンセラー協会 |
| 試験形式 | 終活カウンセラー協会認定講師:講義+試験 1級:レポート+講習受講 2級:筆記 |
| 試験日程 | 随時 |
| 合格発表 | 随時 |
| 合格率 | 終活カウンセラー協会認定講師:ー 1級:60~70% 2級:90% |
| 受験料 | 終活カウンセラー協会認定講師:300,000円 1級:48,000~53,000円 2級:16,000円 |
終活カウンセラーの資格は、終活カウンセラー協会が主催する公式資格で、「認定講師」「1級」「2級」の3つに分かれています。
最上位の認定講師は、講義と試験で高度な知識が求められる資格で、受講料は30万円と高額ですが、取得後は終活カウンセラーを育成できる立場になれるのが大きな特徴です。
中級の終活カウンセラー1級は、レポート提出と講習受講が必要で、合格率は60〜70%。終活相談を実務レベルで行いたい人に向いています。
入門となる終活カウンセラー2級は筆記試験のみで受験でき、**合格率90%**と高いのが特徴です。終活の基礎を身につけたい人や家族のために学びたい人に最適です。
いずれも日程・合格発表は随時で、学びたいタイミングで受験しやすい点もメリットです。
試験内容
| 区分 | 試験内容 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 終活カウンセラー協会認定講師 | 協会指定の 講義の受講+試験 を実施し、終活全般の知識だけでなく「教える力」も問われる内容 | 終活分野の専門家として活動するための上位資格 |
| 1級終活カウンセラー | レポート提出+講習受講 が必須。実務寄りの内容で、相続・葬儀・介護・お墓など終活全体を“提案できるレベル”が求められる | 合格率は 60〜70% とやや難易度高め |
| 2級終活カウンセラー | 終活の基礎知識を問う 筆記試験。相続や介護の基本用語、終活の流れ、必要書類などの初歩が中心 |
2級 終活カウンセラー — 終活の基礎知識を身につけるエントリーレベル
2級では、まず約6時間の講習を受けた後に筆記試験が行われます。
講習および試験を通じて、相続、葬儀、お墓、介護、保険、終活ノート(エンディングノート)の書き方など、終活に関する基本的な知識を体系的に学びます。
自分自身や家族の終活準備に必要な情報を理解し、相談を受けたときに基本的な対応ができるレベルが目的です。
1級 終活カウンセラー — 他者の終活を支える実践レベル
1級を受験するには、2級取得が前提となり、さらに協会が主催する勉強会への参加が条件となります。
試験内容は「事前レポートの提出」と、2日間にわたる講習および試験によって構成され、終活ノートの作成支援や、相談者の人生の終末に関する悩みに寄り添いながら対応できる知識とスキルを習得することが求められます。
他者の終活に実務的に関わりたい人のためのステップです。
終活カウンセラー協会認定講師 — 終活カウンセラーを育成できる最高ランク
認定講師は、1級資格取得者で、かつ協会の勉強会参加や過去の「エンディングノートの書き方セミナー講師養成講座」の受講が条件となります。
講習は6日間(1日6〜7時間程度)、加えて最終試験(短時間の試験)があります。この講座を通じて、終活知識だけでなく、講師として人に教える力やプレゼンテーションスキルを身につけ、終活セミナーの開催や他の受講者の育成ができるレベルに到達します。
終活カウンセラー取得のメリット
終活カウンセラー取得のメリット
- 終活全般の知識を効率よく習得できる
- 資格保有が信頼につながり、仕事で活かしやすい
- 自分や家族の老後設計にも直接役立つ
終活全般の知識を効率よく習得できる
終活カウンセラー資格の大きなメリットは、相続・葬儀・介護・お墓など終活に必要な情報を体系的に学べることです。
終活は複数の専門分野が絡むため、独学だと必要な情報が散らばりがちですが、資格講座では重要項目をまとめて学べます。
特に「終活の基礎をしっかり学びたい」「家族の終活準備に備えたい」という人にとって、効率よく全体像をつかめる点は大きな強みです。
資格保有が信頼につながり、仕事で活かしやすい
終活カウンセラーを取得すると、資格を持つことで専門性を示せるため顧客からの信頼が得やすくなるというメリットがあります。
葬儀・保険・不動産・介護業界などでは終活に関する相談が増えており、「終活の知識があるスタッフ」は選ばれる理由になりやすいのが現状です。
資格取得によって、
・終活相談の質が向上する
・顧客への提案力が強化される
・キャリアの幅が広がる
など、実務に直結する効果が期待できます。
自分や家族の老後設計にも直接役立つ
終活カウンセラーは、仕事だけでなく自分自身や家族の終活にも活用できる実用的な資格です。
介護の選択肢や相続の流れ、終末期医療の考え方など、将来必ず向き合うテーマを事前に理解しておくことで、トラブルや不安を大きく減らせます。
「何から手を付ければいいかわからない」という人でも、資格学習を通して終活の準備を着実に進められ、安心して将来に備えることができます。
終活カウンセラー取得のデメリット
終活カウンセラー取得のデメリット
- 資格だけで高収入につながるわけではない
- 講座費用が高めで、気軽には取得しにくい
- 終活の知識は更新が必要で、継続的な学習が求められる
資格だけで高収入につながるわけではない
終活カウンセラーは専門知識を証明できますが、資格単体で高収入を得られるタイプの資格ではありません。
収益につなげるには、葬儀・保険・不動産・介護など、関連業界での実務経験や営業スキルが必要になる場合があります。
「資格を取っただけで仕事が増える」というわけではない点は押さえておきましょう。
講座費用が高めで、気軽には取得しにくい
終活カウンセラーは、級によっては受講料が高く、初期費用が大きいのがデメリットです。
特に上位資格や講師資格になると数万円〜数十万円の費用が発生するため、自己投資としては慎重な判断が必要です。
終活の知識は更新が必要で、継続的な学習が求められる
終活は、法律改正・介護制度・葬儀の形態などが変化しやすい分野です。
そのため、資格を取得した後も情報をアップデートし続ける必要がある点は見落としがちなデメリットです。
資格を取って終わりではなく、最新情報に触れ続ける姿勢が求められます。
終活カウンセラーに課するよくある質問(Q&A)
-
終活カウンセラーは本当に意味ありますか?
-
終活カウンセラーは「意味ない」と言われることもありますが、実際は終活の専門知識を体系的に学べる数少ない資格です。
葬儀・保険・介護・不動産など終活関連の仕事に携わる人にとっては、顧客からの信頼性が高まり、提案の質が上がるメリットがあります。「家族の終活を整理しておきたい」「仕事で終活の相談が増えている」という人にとっては、十分取得する価値があります。
-
終活カウンセラーは独学で取得できますか?
-
2級は基礎知識が中心のため、テキスト学習だけで独学合格が可能です。
ただし1級になるとレポート提出や講習受講が必須となり、実務的な内容が多くなるため、独学よりも講座の活用が効率的です。独学で目指すなら、まずは合格率の高い2級からの取得がおすすめです。
-
終活カウンセラーの資格だけで仕事につながりますか?
-
資格単体で即仕事になるわけではありませんが、終活に関する相談対応力が上がり、関連業界での評価が高まるのが特徴です。
特に以下の業界では実務で役立つ場面が多く、キャリアの幅を広げやすい資格です。・葬儀・仏壇・墓石業界
・保険業界(生保・損保)
・不動産、相続コンサル
・介護・福祉サービス「終活の知識があるスタッフ」を求める企業は増えており、転職や副業にも活かしやすい資格です。
-
終活カウンセラーの難易度はどれくらいですか?
-
2級は合格率約90%で、初心者でも取りやすい難易度です。
1級は合格率60〜70%とやや難しく、終活全般の深い理解と実務的な知識が求められます。「終活を基礎から学びたい人」は2級、
「仕事でしっかり活かしたい人」は1級取得を目指すのが一般的です。